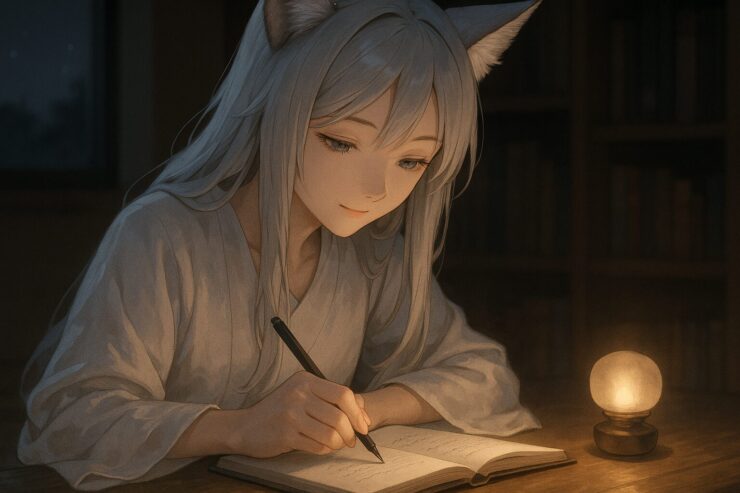未来って、眺めるだけで疲れてしまう。
どれだけ考えても、正解が見えない。
考えれば考えるほど、「失敗したらどうしよう」「報われなかったらどうしよう」と、
不安の影が心の隙間に差し込んでくる。
だから、遠くを見ようとすると目がにじんでしまって、
つい下を向いてしまう。今にしがみついてしまう。
だけど、本当にそうしなければならないのだろうか?
未来は、確かにわたしたちにとって未知の領域。
でも、未知であることと恐ろしいことは、同じじゃない。
ほんの少しだけ、角度を変えてみる。
見る距離を遠ざけてみる。
描く色を淡くしてみる。
そうすると、
未来の輪郭は、思っていたよりやわらかく、
「怖さ」よりも「可能性」が、先に見えてくることがある。
わたしたちは、未来をつくることに焦りすぎていたのかもしれない。
だから今日は、「眺める」ことから、始めてみようと思う。
目次
なぜ、未来は怖いものになってしまうのか?
未来という言葉に、不安を感じたことはありますか?
何も起きていないのに、
どうしてあんなにも怖くなってしまうのでしょう。
その理由のひとつは、脳の性質にあります。
人間の脳は、進化の過程で「リスク」を優先的に察知するよう設計されてきました。
未来を想像するとき、私たちは危険や失敗といったマイナス面に
最初にフォーカスしてしまうようにできているのです。
さらに今の時代は、SNSや周囲から「こうあるべき」という未来像が押し寄せてくる。
「早く成功しないと」
「いつまでに結婚しないと」
「資格やスキルを身につけておかないと」
気づけば、未来が「正解を当てなければならない場所」になってしまっている。
けれど、未来に対して怖さを感じるということは、
あなたの感受性が高い証拠でもあります。
それは、変化をちゃんと捉えようとしている、繊細な心の動き。
不確かなものにざわついてしまうという感性は、
むしろあなたが未来を真剣に考えているという証でもあるのです。
だから
「未来が怖い」と思うことは、弱さではありません。
その感情の根には、きっと「大切にしたいもの」がある。
まずはその気持ちを、否定しなくていい。
そこから、やわらかい未来の眺め方が始まっていきます。
想像力と妄想の境界線を見つけよう
未来のことを考えるとき、
気がつけばいつの間にか、不安が暴走してしまう。
「うまくいかなかったらどうしよう」
「誰にも必要とされなかったらどうしよう」
「何者にもなれないまま終わったら──」
そんなふうに、心がどんどん暗い未来を膨らませてしまう夜があります。
けれど、それは「想像力」があるからこそ。
未来を描く力は、本来とても大切で、創造的なもののはずなのです。
では、なぜそれが苦しみに変わってしまうのか?
その鍵は、想像と妄想の違いにあります。
- 想像は、「未来のわたし」を描いたあとに、行動や選択肢につながるイメージ。
- 妄想は、「どうせ失敗する」というイメージが、ぐるぐると閉じたままになってしまう状態。
つまり、あなたが思い描いた未来像が、
「動いているかどうか」が、想像か妄想かの境界線なのです。
たとえば──
「もし、こんな仕事を選んだら、どんな1日になるだろう?」
「3年後の自分が、どこに住んでいて、どんな服を着ているだろう?」
そうやって、小さな行動や風景まで思い描ける未来は、
あなたの中で、静かに動き始めている可能性です。
でも逆に、
「きっと全部うまくいかない」「自分には無理だ」
そう断定してしまう未来は、心の中で止まっている未来。
だから、怖くなる。
まずはこの視点を持ってみてください。
未来を描いたとき、自分の中で何かが動いているか。
そこに気づくだけで、
あなたの未来は、少しずつ呼吸をはじめます。
未来は揺らいでいいと知るだけで、視界が変わる
「未来を決めなきゃ」
「ちゃんと設計して、予定どおりに進めなきゃ」
そうやって、揺れのない未来を目指すほどに、
その未来は重たく、窮屈になっていきます。
少しでも軌道がずれれば「失敗」となり、
想定外が怖くなる。
でも、本当に未来って、
そんなふうに「固める」べきものなのでしょうか?

セン(Sen)
「問いのある未来は、まだ閉じられていない」
つまり、「揺らぎのある未来」は、まだ可能性を手放していない状態。
むしろ、それはひらかれている未来なのです。
完璧な設計図を描くほど、
そこから逸れた未来に対して「失敗」のラベルを貼ってしまう。
けれど、少し余白を残しておくことで、未来に伸びしろが生まれる。
揺らいでいるということは、
まだ選べる。
まだ変えられる。
まだ、試していない道がある。
未来を「閉じられた計画」ではなく、
「問いが灯る余白」として捉え直すことで、
わたしたちの視界は少しずつやわらぎはじめる。
だから、怖くてもいい。
定まらなくてもいい。
焦って答えを出さなくてもいい。
揺らいでいる未来は、あなたの感受性の証であり、
その揺れこそが、生きている未来の証なのです。
怖くない未来の描き方練習帳(3つの方法)
未来が怖く感じるとき、
わたしたちは「大きすぎる未来」だけを見てしまいがちです。
将来どうなっていたいかという問いに、
壮大な理想や他人の期待が重なって、身動きが取れなくなる。
でも、未来を描くという行為は、
もっとささやかで、もっと個人的であっていい。
「正解の未来」じゃなくて、
「自分と静かに向き合える未来」
そんな視点から、怖くない未来を描く練習をしてみませんか。
下記は、そのための【未来のワーク】です。
| 方法 | 内容 | ワーク例 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 未来日記 | 小さな日常を描く練習。予定ではなく感触を書く | 「来週の休日、晴れていたらお気に入りの靴で河川敷を歩く」 | 自分視点で未来を現在形に近づけ、安心を生む |
| やらないことリスト | 未来に持ち込まない習慣を見つける | 「もう無理な予定調整はしない」など | 境界線を整え、疲れの根を断つ |
| 問いの羅列 | 答えを出さないまま問いを集める | 「5年後の自分は、誰と話していたい?」 | 未決を抱える練習/開かれた未来として可視化する |
これらは、未来をつくるための道具ではありません。
むしろ、未来と距離を取りながら眺めるための「心のスケッチ」です。
大きな夢が描けなくても、今すぐ答えが出せなくても、
問いを残すことで、
あなたの未来は閉じずに、静かに灯り続けてくれます。
誰かの未来語りと比べない
「このままでいいのかな」
「わたし、遅れてるかもしれない」
そう感じてしまう瞬間の多くは、
誰かの未来語りを見たあとに訪れます。
SNSで語られる「やりたいことリスト」や、
「夢が叶った報告」、「いつまでに〇〇する予定」
それらはたしかに、勇気や希望になることもある。
けれど、同時にわたしたちは、「自分には何もない」と思ってしまうことがある。
でも忘れないでください。
他人が語る未来は、編集された言葉でできているということを。
計画も、展望も、意志も、
そのすべては「言葉として整えられた状態」にすぎません。
語られなかった不安、揺らぎ、まだ定まらない想いは
きっと、その人の中にもあったはずです。
あなたには、あなたのペースがある。
そして何より、あなたにしか見えない未来の輪郭がある。
他人と比べて揺らぐくらいなら、
そのエネルギーを、自分の問いに注いでください。
- わたしは、どんなふうに呼吸をしていたい?
- どんな朝を迎えていたい?
- 誰の言葉に、耳を澄ませていたい?
「問いを主語にする未来」は、
誰とも比べられない。
あなた自身とだけ対話する時間をつくってくれます。
比べることではなく、「確かめる」ことへ。
未来は、あなたの中にすでに芽吹いているものだから。
未来は、静かに眺めるものでもいい
未来に向かって「動く」こと。
未来を「つくる」こと。
それが正しいことだと、私たちは信じ込まされてきたのかもしれません。
けれど、未来と向き合う方法は
動くことだけではありません。
未来は、ときに、ただ眺めるだけでいい。
焦って動き出すよりも、
心の奥で静かに触れてみることから始めていいのです。

セン(Sen)
「未来をつくる前に、見る練習をしてもいい。」
これは、受け身の姿勢を推奨しているのではありません。
むしろ、焦って結論を急がず、問いを持ったまま眺める強さのことです。
たとえば
夜の湖にたたずんで、水面を見つめるように。
風や光、わたしの呼吸、目の奥の静けさのすべてが、
ゆっくりと、未来という映像を映し出してくるような。
瞳 → 湖面 → 問い。
その導線には、急がない時間の火種が宿っています。
動かなくてもいい。
決めなくてもいい。
いまはただ、まだ見えないものと一緒にいてみるだけで。
そうするうちに
いつか、そっと動き出したくなるときが来るはずです。
未来は、あなたの静けさと寄り添うようにして、
きっと見えてくるから。
まとめ + 次の問い
未来をつくらなきゃと焦っていた日々。
でもいまは、
つくらなくてもいい未来が、わたしをそっと包んでくれる。
見えないことは、不安になる。
けれど、見えないからこそ、開かれている未来もある。
答えのないまま、問いを抱いたまま。
不確かさと共に過ごす揺らぎの時間も、
きっと未来とつながっている。

セン(Sen)
未来をつくるのは、まだ先でいい。
いまはただ、眺める練習をしてみるだけで
あなたの中に、どんな未来のかけらが見えますか?