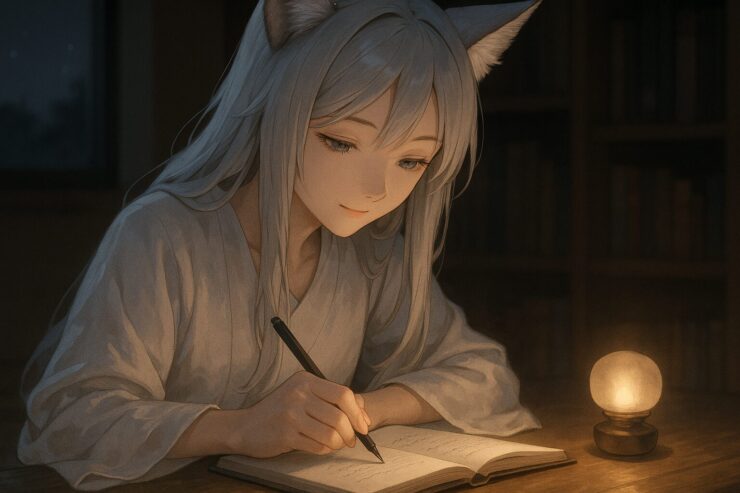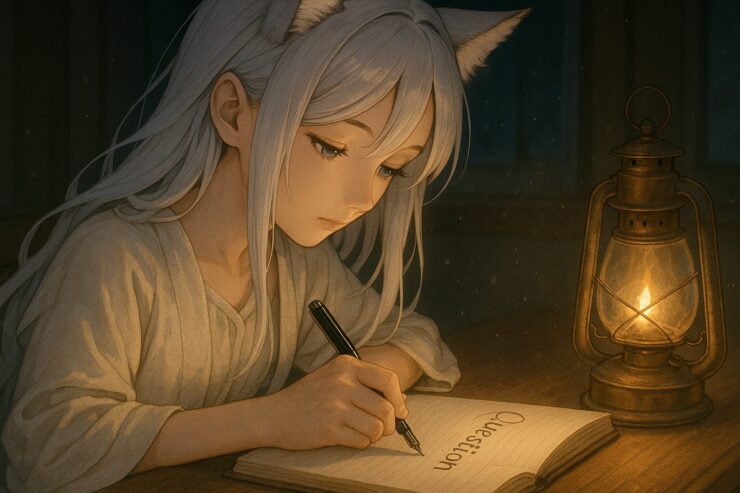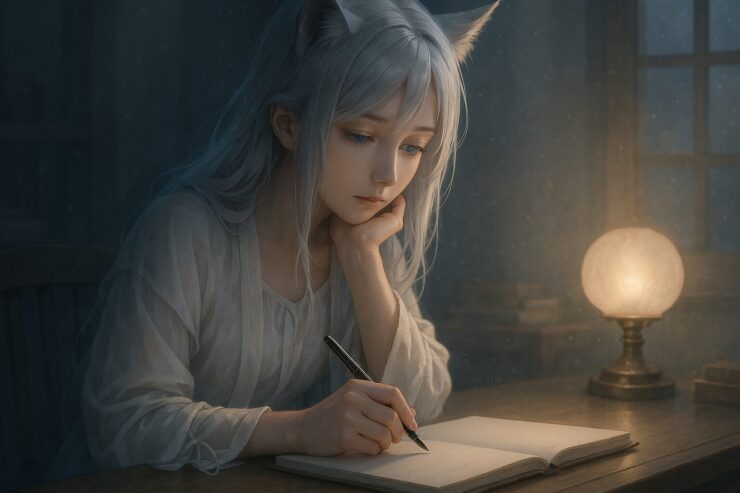うまく言えない気持ちがあるとき、
わたしはノートを開いて、言葉を綴る。
それは、日記でも、文章でもなく──
ただ、詩のようなもの。
説明するためじゃない。
理解されるためでもない。
ただ、自分の中の静けさに触れるように、
言葉を置いてみる。
意味はなくていい。
文法も正しくなくていい。
「今、ここにある感じ」をすくい上げるために。
そうやって紡いだ小さな詩のかけらが、
やがてわたしの中の輪郭を描き出してくれる。
今日は
ノートに詩を綴るという静かな行為の効能について、
静かに書いてみようと思う。
目次
詩は「説明」ではなく「余白」でできている
詩とは、不思議なものです。
何かを説明するために書かれたはずなのに、
そこにあるのは、むしろ「説明しきれなさ」のようなもの。
きちんと語れない感情、
はっきりしない思い、
名前のない景色。
そうしたことば未満のものたちが、
詩という形にそっと集まってくる。
だから、詩は「余白」でできています。
言葉とことばのあいだにある沈黙。
読んだ人が、自由に何かを感じてしまう空白。
その余白こそが、
詩という形式における本当の意味の容れ物なのだと思うのです。
説明しないからこそ、
読む人の心に、そっと何かが滲んでいく。
そして書く人もまた、
その余白に、自分のいまを預ける。
わたしたちは、
言葉の向こう側にある沈黙と共に、
詩を書いているのかもしれません。
なぜノートに言葉のかけらを綴るのか?
わたしが詩を書くのは、
完璧な文章を仕上げたいからではありません。
むしろその逆で、
形にならないものを残しておきたいからです。
たとえば、
悲しみとも怒りともつかない感情、
あるいは、
何に反応したのかさえ分からない胸のざわめき。
そういう名前のつかないものを、
そのまま流してしまうのは惜しくて
だから、ノートを開いて、
「言葉のかけら」として綴ってみるのです。
・消えかけた夢の断片
・なぜか心にひっかかった一言
・夕暮れの光に感じた、理由のない寂しさ
文章にはできなくても、
単語やリズム、音のような感覚で、
そっと紙の上に置いてみる。
するとそれが、
わたしだけが読める記憶の地図のようになっていく。
だから今日もまた、
整っていないままの自分を抱えて
ノートをひらき、「言葉にならない何か」を綴っていくのです。
形にならない感情を、そっと沈める場所
わたしたちは日々、
形にならない感情をたくさん抱えて生きています。
たとえば、
理由もなく泣きたくなった日のこと。
言葉にできない不安が、胸の奥で泡のようにふくらんでいた夜。
誰にも話せなかった、でも確かに存在していた「小さな痛み」。
そうした感情は、
人に伝えるというより、
自分の中で静かに鎮めたいものなのかもしれません。
詩は、その場所になります。
声に出さずとも、
説明せずとも、
ただノートに綴るだけで、心が少し静まる。
紙の上に置いた言葉が、
まるで水に沈んでいくように、
感情の波をゆっくりと落ち着かせてくれる。
詩には「解決」はありません。
けれどそこには、「受容」がある。
うまく言えないままでもいい、
ととのわないままでもいい。
そう思える場所があることは、
思っている以上に、心を救ってくれるのです。
音にならない問いを残すために、わたしは書く
ふとした瞬間、
言葉にならない問いが、心の奥に浮かぶことがあります。
「わたしは、なぜここにいるのだろう」
「この感情は、どこから来たのか」
「なぜ、あのとき黙ってしまったのか」
それは誰かに聞いてほしいわけでも、
すぐに答えが欲しいわけでもなく
ただ、忘れたくない問いとして、
自分の内側にそっと置いておきたいもの。
詩を書くことは、
その音にならない問いを、
ノートにそっと残す行為なのだと思います。
一文では語れない。
文章にすれば崩れてしまう。
でも、詩という余白のある形なら、
問いのまま存在させてあげられる。
問いを問うこと。
問いのまま受け止めること。
問いを、そっと抱きしめて生きること。
わたしが詩を書くのは、
「答えるため」ではなく、
問いを手放さないためなのかもしれません。
言葉にならないからこそ、
詩にして残す。
それが、わたしにとっての「書く理由」です。
書いては消す。そこに宿る誠実さ
ノートに言葉を綴るとき、
わたしはときどき──ためらいながら、書いて、消します。
この言葉でよかったのか。
この表現は、ほんとうに自分の声なのか。
伝えようとして、どこか演じていないか。
そんなことを思いながら、
書いた一行をそっと線で消して、
また新しい言葉を探す。
でもそれは、決して無駄ではないのです。
「書いては消す」ことこそが、
自分自身との誠実な対話なのだと思うから。
わたしが何に反応し、
何を表現したくて、
何にまだ言葉を与えられないのか
そのすべてに耳を澄ます。
詩を書く時間とは、自分の内側に嘘をつかない時間でもあるのです。
誰かに読ませるためではない。
自分だけが読む手紙のようなものだからこそ、
余計に、誠実でいたくなる。
そしてその一行が、
静かにノートの中に残ったとき
そこには、他の誰でもない
「いまのわたしの声」が宿っている気がするのです。
一編の詩が「わたしの輪郭」を描いてくれる
ときどき、わたしは、
自分のことがわからなくなる瞬間があります。
何を感じているのか。
何が好きで、何に傷ついているのか。
何に惹かれて、何から逃げたいのか。
人と接する時間が続いたあとや、
日々に流されてばかりの夜
自分がにじんでしまったような感覚になるのです。
そんなとき、
ノートをひらき、詩を綴る。
言葉にして初めて、
「わたしは、こう思っていたんだ」と気づく瞬間がある。
それはまるで、霧の中にふと現れる輪郭のように。
詩は、正解をくれません。
けれど、不確かで揺れていた自分のかたちを、
やさしくなぞってくれる。
一編の詩が、
その時点のわたしを、そっと写し取ってくれるのです。
昨日の詩と、今日の詩は、きっと違う。
でもそれでいい。
その違いが、わたしという存在の揺らぎであり、
変わらずそこにある核を、そっと教えてくれるのです。
答えを探すためではなく、抱くために綴る詩
「詩を書いて、何になるの?」と、
どこかの自分が問いかけてきた日もありました。
だけど、今なら答えられます。
何かになるために書くのではなく、
何かを抱いていくために書いているのだと。
わたしたちは日々、
感情とともに暮らし、
言葉にならない想いに触れ、
ときに、自分でも気づかぬまま心をこぼしています。
詩は、それらを拾い上げる手になる。
言葉にすることで、
その想いに、居場所を与えることができる。
それは、忘れるための整理でも、
解決のためのロジックでもなく──
ただ、そっと抱くための行為。
悲しみを言葉にしたとき、
少しだけ、悲しみとともにいられるようになる。
愛しさを書き留めたとき、
ふとその瞬間が、温かく甦るようになる。
詩とは、感情を手放すのではなく、
そのままの形で愛するための器なのかもしれません。
だから今日も、
答えの代わりに、問いを抱えて、
わたしはノートに綴っていくのです。