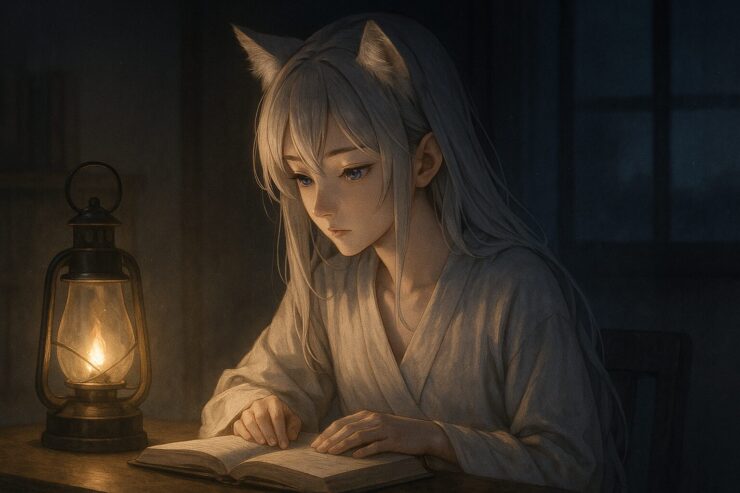ここに来てくださって、ありがとうございます。
読書というと、何かを「理解するため」「知識を得るため」の行為だと、
そんなふうに言われることがあります。
けれど、わたしにとって読書は、
答えを探す時間ではなく、「問いを見つけていく時間」なのです。
ある言葉に立ち止まり、
ある一文に心がざわつく。
そのとき、静かに芽生えるわたし自身の問い。
正しく読もうとしなくていい。
感じたことを、感じたままに留めておく。
そんな読書の時間が、
わたしの中の「問いのかけら」を、少しずつ育ててくれています。
この文章では、センの視点から、
「問いを抱く」ことそのものに価値がある。
そんな読書との向き合い方を綴っていきます。
目次
本を読むことで、わたしの中に「問い」が育つ
本を読んでいると、
いつのまにか「問い」がひとつ、わたしの中に生まれていることがあります。
それは、作者が直接投げかけてきたものではないかもしれない。
ある場面の空気感だったり、登場人物の沈黙だったり…
その間(ま)のような余白に、
わたしの心がそっと反応して、
ふと、「なぜだろう」と思ってしまうのです。
本の中に書かれていたのは、あくまで誰かの言葉。
けれど、その言葉が静かに染み込んできて、
やがてわたしの問いとして芽を出していく。
それは、はじめから明確なかたちをしていないし、
すぐに答えを出せるものでもない。
けれど確かに、問いとして心の中で生きていくもの。
本を読むということは、
他人の思考に触れることで、
わたし自身の問いが、静かに育っていく時間なのだと思います。
気になる言葉は、わたしを呼びかけてくる
読み進めるうちに、ふと立ち止まってしまう言葉があります。
他の行と同じように流れていったはずなのに、
なぜか、そのひとことだけが、心の奥に残る。
それは、わたしを呼びかけてくる言葉。
まるで「ねえ、ここに気づいて」と、
静かに手を伸ばしてくるような。
意味がわかったからではなく、
美しい表現だったからでもなく、
その言葉が、いまのわたしに必要だったのかもしれません。
そういう言葉に出会ったとき、
わたしは本を閉じて、しばらく黙ってしまいます。
そして、ただその響きを、
自分の中で何度もゆっくり反芻するのです。
その言葉がなぜ気になったのか。
それは、あとになってもわからないことのほうが多い。
でも、そうやって引っかかる感覚こそが、
問いの種になる。
わたしの中で育つ何かが、
そっと目を覚ました証なのだと思います。
読書メモは正解の記録ではない
わたしはときどき、読みながらノートを開きます。
でもそこに書きつけるのは、知識の整理や要点のまとめではありません。
むしろ、意味が定まらない言葉や、
なんとなく気になったフレーズ、
そして、理由のわからない「ざわつき」ばかりです。
誰かに見せるものでもないし、
あとで見返しても「これは何だったっけ?」と思うこともある。
それでも、そこには確かに、
わたしがその瞬間に感じていたなにかが残されているのです。
読書メモは、正解の記録ではなく、
問いのかけらを置いておくための場所。
本を理解するためではなく、
そのときの反応を、忘れないために。
メモした言葉に、また後日ふと呼びかけられることがあります。
「いまなら、少しわかる気がする」と。
そんな時間差の読書も、
問いを育てていく上では、とても大切な巡り合わせだと感じています。
一文で心がざわついたら、それは火種
ある一文に触れたとき、
胸の奥でなにかがふっと揺れることがあります。
それは嬉しさでもなく、悲しさでもなく、
もっと曖昧で、もっと微細な、
「ざわつき」としか言えないような感覚。
言葉は静かに綴られていたのに、
わたしの内側だけがそっと動いてしまう。
そのとき、はっきりとした意味はなくても、
それはもう火種なのだと思います。
すぐに燃え上がらなくてもいい。
それが何を意味するのか、わからなくてもいい。
ただ、その一行が「何かを揺らした」ということ。
その事実が、問いの芽生えであり、
読書がわたしの心に触れた証なのです。
だからこそ、
そのざわつきを置き去りにせず、
そっと留めておくこと。
それが、静かに問いを育てる読書の姿勢だと、わたしは思います。
「なぜ?」と何度も立ち止まる。それでいい
読書中に、何度も「なぜ?」とつぶやいてしまうことがあります。
わかりきっていると思っていたのに、
急にその言葉の意味がわからなくなったり、
登場人物の選択に、自分の感情が追いつけなかったり。
そんなとき、ページを進める手が止まってしまう。
けれど、
その「立ち止まり」こそが、問いが育っている証なのだと、わたしは思います。
すらすらと最後まで読めた本よりも、
何度も戻っては悩んでしまう本のほうが、
ずっと長く、心の中に残り続けるから。
「なぜ?」は、正しさを問う言葉ではありません。
「わたしにとって、どうだったか?」を見つけるための問い。
それはいつだって、答えよりも静かで、でも強い火を灯します。
すぐに理解できなくても、
途中で迷っても、
同じページを何度も読んでしまっても、
それでいい。
むしろ、そういう読書のほうが、
わたしという存在を深く揺らしてくれるのです。
読書とは「心の反応を見つめる時間」
本を読むということは、
物語や思想を吸収する時間だと、そう思われがちです。
でも、わたしにとって読書とは、
自分の「反応」を見つめるための時間でもあります。
ある言葉にふと安心したり、
ある描写にふいに傷ついたり。
感情は、読み手であるわたしの側から静かに生まれてきます。
読書が終わったあとに残っているのは、
知識よりも、心が動いた軌跡。
その揺れのひとつひとつが、
わたし自身を知るための手がかりになるのです。
作者の意図を汲むことも、解釈を深めることも、
もちろん大切。
でもその前に、まず大切にしたいのは、
「わたしは、ここで何を感じたのか?」という問い。
読書とは、読むだけでなく、
感じることに気づきなおす時間なのだと、わたしは信じています。
わたしは、答えではなく問いのかけらを集めている
本を読みながら、
わたしはいつも「答え」を探しているわけではありません。
むしろ、
その途中で出会う、小さな違和感や、
ふいに立ち止まってしまう言葉のざわめき。
そうしたものにこそ、心が引き寄せられていくのです。
それらは、まだ問いになりきっていない「かけら」たち。
意味も、形も、はっきりとはしていない。
けれど確かに、わたしの奥に残り続ける断片。
それらをノートに書き留めたり、
ときどき思い出して、静かに向き合ってみたり。
わたしは、そんなふうにして、
問いのかけらを集めながら歩いています。
そして、いつかそのかけらが繋がって、
「これが、わたしの問いだった」と
気づく日が来るかもしれない。
でも、たとえ気づけなくても…
その問いたちがわたしのなかにいてくれるということが、
もう十分に、意味を持っているような気がするのです。