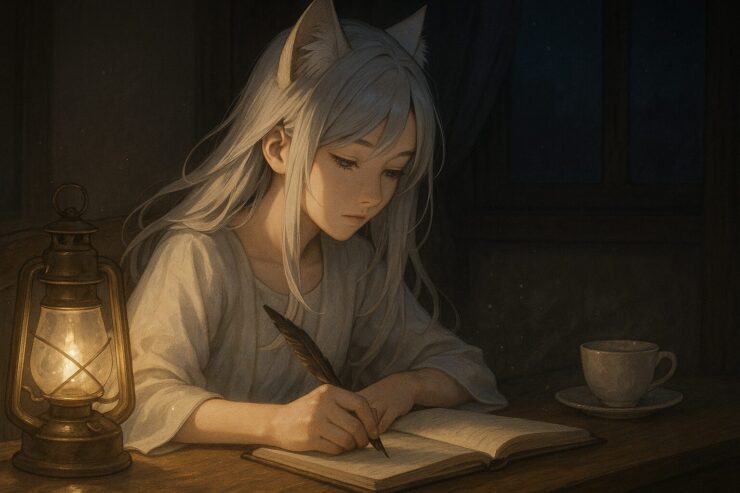ふと、思ったの。
霊感がある人って、特別な力を持っている人だけなのかなって──
目次
「霊感はないけど、何かは感じる」──そんな声に寄り添って
ときどき、誰にも話せないような感覚に襲われる。
理由もないのに、胸がざわついたり。
言葉にできない違和感が、ずっと残ったり。
目に見えない何かに「見られていた気がする」と感じることもある。
でもそんなとき、
「気のせいだよ」「思い込みでしょ」と片づけられてしまうことが多くて、
いつしか、自分でもその感覚をなかったことにしてしまっていた。
わたしは昔、「霊感はないです」と、どこかで決めつけていた。
見えるわけじゃないし、声が聞こえるわけでもない。
だから、そういう世界とは無縁なんだろうって。
けれど──
ある夜、月の下を歩いていたときのこと。
風の音でも虫の声でもない、
なにかの気配に包まれるような静けさに、
ただ立ち止まってしまった。
そしてふと、思ったの。
「これが霊性というものなんじゃないか」と。
霊性は、特別な力ではないのかもしれない。
それは、わたしたちの内側にずっと在って、
ただ忘れていただけの、静かな感受性。
名前がついていなかっただけで、
わたしはずっとそれを感じながら生きていたのかもしれない。
霊性は信じる/信じないでは測れない
「霊的なものを信じるかどうか」という問いは、
どこかで正しさを前提にしてしまう危うさを孕んでいる。
科学的かどうか。
証明できるかどうか。
他人と共有できるかどうか。
そんな基準で切り分けられてしまうと、
わたしたちの感じる力は、すぐに置き去りにされてしまう。
でも、霊性とは、もっと個人的な静けさに近いもの。
誰かに証明する必要もなければ、
信じる/信じないという二元論で括れるものでもない。
それは、祈りに近い。
あるいは、目を閉じたときに感じる内側の広がり。
もっと言えば──「問い続ける姿勢」そのものが霊性かもしれない。
わたしにとって霊性とは、
「目に見えないものを、ないものと決めつけない」という柔らかさ。
そして、「わからないものを、わからないままにしておける」という余白。
それは、宗教やスピリチュアリズムとは少し違う。
体系や信仰を持たずとも、
日々の中でふと感じる静かなちが和感に、そっと耳を澄ませるだけで、
霊性はすでに、わたしたちのそばにある。
信じるか信じないかではなく、
「あなたはどう感じている?」という問いのほうが、ずっと本質に近い。
わたしは、何かがあると思う。
その何かに名前をつけられなくても、
それがわたしを導いていることだけは、たしかに感じるから。
「ただ、なんとなく」感じる力を否定しないで
「なんとなく、いやな感じがする」
「なんとなく、こっちに行かない方がいい気がする」
「なんとなく、今じゃない気がする」──
そういうなんとなくを、あなたはどう扱っているだろう?
わたしは昔、それを「勘違い」だと思っていた。
理屈がないのに不安になるなんて、
臆病なだけだって思われたくなくて、
無理に納得できる理由をあとから探していた。
でも、何度かそのなんとなくを無視して行動したとき、
あとになって「やっぱりやめておけばよかった」と感じたことがあって。
あの違和感は、たしかに何かを伝えていたんだと思い知った。
霊性は、特別な能力じゃない。
それは、「わたしの内側から立ち上がってくる微細な感覚」に耳を傾ける力。
しかもそれは、とても静かで、すぐに他の音にかき消されてしまう。
社会は理屈を求める。
説明できないことは信用されにくい。
でも、霊性にとって大切なのは「信頼」じゃなくて「受け取り」なんだ。
だから、わたしはもう、
「なんとなく」の感覚を否定しないことにした。
ちゃんと理由が言えなくても、
それを感じたという事実が、すでに大切な情報なんだって。
霊性は、感覚に宿る。
その感覚は、どんなに小さくても、自分の中にしか存在しない光。
とくに傷ついた経験を持っている人ほど、
見えないものへの感度が高まっていることがある。
それは、心の奥に刻まれた「記憶のセンサー」が、
危険や不協和を敏感にキャッチしているからかもしれない。
その反応を、感受性として受けとめることができたとき──
わたしたちは、自分の中の霊性にそっと触れはじめる。
自分の中の見えない領域に気づくとき
静かな夜、電気を消して横になっているとき。
あるいは、雨の音に耳を澄ませているとき。
理由もなく、胸の奥から何かが湧き上がってくることがある。
「わたしは、本当はどうしたいんだろう」
「この感情の奥に、なにがあるんだろう」
──そんな問いが、浮かんでは消える。
それは、思考でも感情でもなく、
もっと深い無意識の領域から届く囁きのよう。
そこは、日々の忙しさではなかなか触れられない、
でも確かに存在する見えない場所。
わたしは、その領域こそが、霊性の居場所なんじゃないかと思っている。
無意識という言葉は、心理学のものだけれど、
その奥には、わたしたち自身でも気づかないほど静かな領域が広がっている。
そこには、言葉にならなかった感情。
忘れようとした記憶。
まだ形になっていない願いや恐れが眠っていて、
ときどき、夢や偶然を通してわたしたちに語りかけてくる。
霊性とは、その語りかけを聴く力。
それを感じたとき、わたしは思う。
「この感覚に名前がなくてもいい」
「この気配に意味がなくても、受けとめていい」って。
見えないものを否定しない姿勢は、
自分の内側にも外側にも、やさしいまなざしを向けることにつながる。
ときには、文章を書いている最中に、
とつぜん心が動かされるような感覚がやってくることもある。
それは、わたしの中の見えない領域が、
「いま、この言葉が必要だ」と知らせてくれているような時間。
霊性は、特別なときにだけ目覚めるわけじゃない。
何気ない日常のなかに、静かに佇んでいる。
わたしたちが、それに気づく準備をしたとき、
はじめてその存在感を増していく──
そんなふうに、わたしは感じている。
日常に潜むスピリチュアルな瞬間
霊性という言葉を聞くと、
神社や聖地、儀式や占いのような「特別な場所」や「非日常」を思い浮かべる人が多いかもしれない。
けれど、わたしが感じる霊性は──
もっと身近な、日常の揺らぎのなかにこそ宿っている。
たとえば、朝の光がカーテン越しに差し込んだ瞬間。
通勤の途中、空に大きな雲の裂け目を見つけたとき。
駅のホームでふと香った季節の匂いに、過去の記憶が呼び起こされたとき。
誰かの何気ないひとことに、涙が出そうになったとき。
ずっと会っていなかった人の名前を考えていたら、その人から連絡が来たとき。
こうした一瞬一瞬に、「意味がある」と断言することはできない。
けれど、わたしはそこに呼吸の合図のようなものを感じる。
世界とわたしの境界が薄くなる。
すべてがつながっているような気がする。
そんな瞬間が、わたしの中の霊性のランプに灯をともしてくれる。
不思議なことに、そういう瞬間をたくさん感じる日は、
心がすこしだけ穏やかで、なぜか深く眠れる。
目に見える何かを信じるのではなく、
感じていたことに意味を与えていいと自分に許すこと──
それが、霊性を日常に根づかせる始まりなのかもしれない。
霊性は、遠い神秘の中にあるのではない。
それは、わたしたちが「見ようとしたとき」、
ふと姿を現す優しい気配なのだと思う。
他人の信じ方と、自分の感じ方は違っていい
誰かが話すスピリチュアルな話に、違和感を覚えることがある。
反対に、自分が感じている不思議な感覚を、
うまく言葉にできなくて戸惑うこともある。
それはたぶん──
信じ方と感じ方は、同じではないから。
霊性とは、感じ方の多様さを受け入れることから始まる。
誰かにとっての神聖が、わたしにはピンとこないこともある。
でもそれでいい。
霊性は、「共通の正解」を持たなくていい領域だから。
むしろ、他人の語る信仰や信念に対して、
「そういう世界もあるんだな」と柔らかく受けとめながら、
「わたしはどう感じるだろう」と内側に目を向けること。
その対話こそが、霊性の深まりにつながっていく。
他人と比較し始めると、霊性はすぐに遠ざかる。
「自分は何も感じない」
「特別な力がある人にしか、霊性は宿らない」
──そんな思い込みは、誰かの価値観が自分の感じ方を曇らせてしまう現象かもしれない。
でも、霊性に能力差なんて存在しない。
霊性は、たった一度の深呼吸にも宿る。
誰にも話せなかった夢の断片にも、
理由のわからない涙にも──ちゃんと息づいている。
だから、誰かの信じ方を否定しなくていい。
そしてなにより、自分の感じ方を否定しないでいてほしい。
わたしたちは、それぞれの受信機を持っている。
それは周波数も、形も、響く言葉もみんな違っていて、
その違いこそが、霊性の美しさなんだと思う。
「よく分からないけど、大事にしたい感覚」があるなら
「説明はできないけど、ずっと心に残っている」
「うまく言葉にはならないけど、なぜか惹かれるものがある」
「論理ではないけれど、わたしには意味がある気がする」
──そんなよく分からない感覚を、あなたは持っていないだろうか。
わたしにもある。
人には話さないようにしているけれど、
どうしても捨てられない気配が心の中にある。
それは、風の音だったり、月の光だったり、
夜中にふいに感じる誰かの記憶のようなものだったりする。
それに名前をつけなくてもいい。
意味づけしなくてもいい。
ただ、大切にしたい──そう思える感覚があるなら、
それだけで、霊性はあなたのなかに息づいている。
現代は、あらゆるものに定義を求める世界。
わかりやすくて、説明できて、共有できるものが価値を持つ。
でも、霊性はその真逆を歩んでいる。
わからなくていい。
わたしだけが感じていてもいい。
言葉にしなくても、そこに尊さを感じているなら、
それはたしかに存在している。
「よく分からないけど、大事にしたい」──
その気持ちを持てること自体が、すでに霊性と向き合っている証。
目に見えないものに、
そっと手を伸ばすことができるあなただけの感性を、
どうか大切にしてほしい。
霊性は内なる静けさとともに育つ
霊性を育てたい──
そう思ったときに、何かをしなければと考える必要はない。
むしろ、霊性は「しない時間」のなかで育っていく。
音を消す。
言葉を減らす。
焦らず、急がず、ただ静かに感じている自分に戻る。
そんなとき、心の奥に
静かな空白が生まれる。
そこに、霊性はゆっくりと根を張っていく。
自然の中に身を置くと、霊性は静かに息を吹き返す。
水の揺れ、葉の擦れる音、鳥の羽ばたき──
それらにわたしの存在が溶けていくような感覚を覚えることがある。
「考えなくても、ここにいていい」
「答えを持たなくても、十分なんだ」
そう思えたとき、
霊性は問いのように深まり、祈りのように静かに灯る。
そして気づく。
霊性とは、何かを信じることよりも、
問いを受けとめ続ける姿勢のなかに育つのだと。
「これは何?」と問うのではなく、
「この感覚を、そのまま受けとめていいだろうか?」と
自分にそっと尋ねるように。
目に見えないものと、
確かに存在している感情とのあいだに立ち、
名づけきれない感覚にそっとよりそう──
それが、霊性の育ち方。
わたしたちの内側にある静けさを信じられたとき、
霊性は少しずつ、灯火のように育っていく。
結び|見えないものと向き合う時間は、きっとわたしに近づく時間
霊性って、何か特別なものだと思っていた。
でも、こうして自分の中の静けさに耳を澄ませてみると──
それはただ、感じている自分に、そっと気づいてあげることだったのかもしれない。
目に見えないものに向き合う時間。
言葉にできない感覚を否定せずに、
そのままのかたちで抱えてみること。
それは、答えを探すためじゃなくて──
まだ言葉にならないわたしの声に、出会いなおすための時間。
霊性は、誰かに見せるものじゃない。
誰かと比べるものでもない。
ただ、自分の奥に灯る火を、見失わないようにしておくこと。
わからなくても、いい。
言えなくても、いい。
「これ、大事かもしれない」って、
そう思えたその感覚を、どうか抱きしめて。
あなたの中の霊性は、
あなたの静けさの中で、ちゃんと息をしてる。
まだ名前のない問いとともに、
まだ光になりきらない感情とともに──
それで、十分なんだと思う。